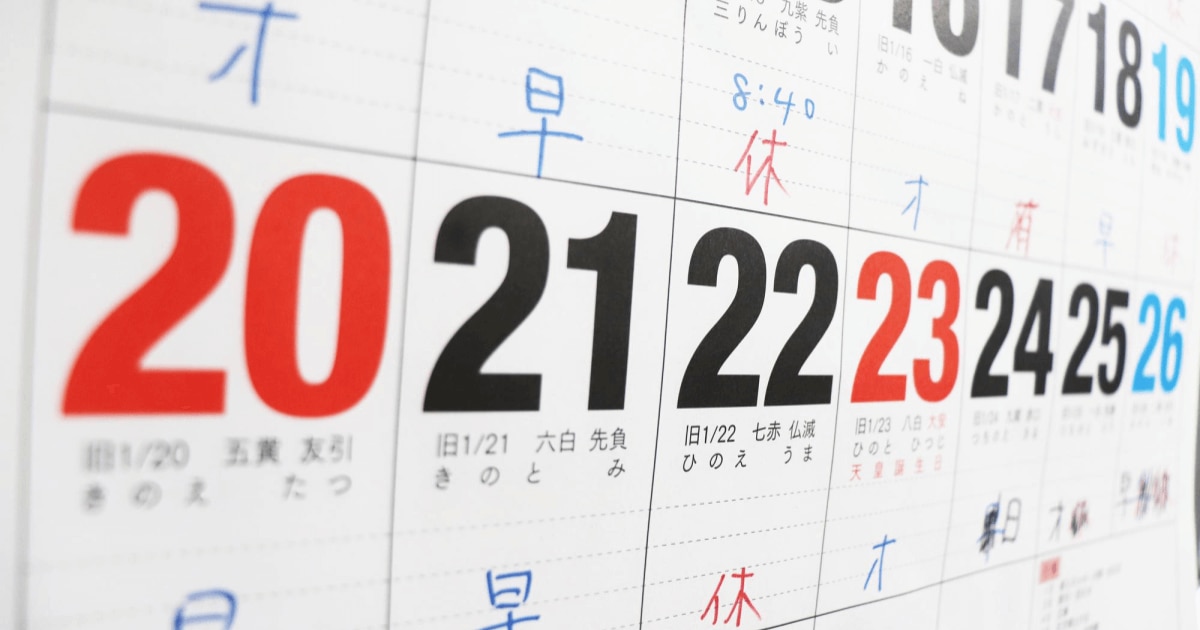
シフト勤務に関する労働基準法と注意点
※2023年5月30日更新
労働基準法には、勤務時間や時間外手当などのさまざまなルールがあります。
宿泊業や飲食業など、シフト勤務を採用している業種については、シフトの管理が複雑になりやすく悩んでいる経営者・管理者も多いのではないでしょうか。
労務違反を防ぐためには、法律で定められたシフト勤務のルールについて理解しておく必要があります。
本記事では、シフト勤務の概要やその位置づけ、法律で定められている具体的な内容について解説します。
目次[非表示]
シフト勤務とは
シフト勤務とは、複数の勤務時間帯において交替制で労働者を勤務させることを指します。
シフト勤務という言葉は、労働基準法で定められる“変形労働時間制”と混同されることもありますが、法的な用語ではないため必ずしも同じことを指すとは限りません。
シフト勤務と変形労働時間制の違い
変形労働時間制とは、1週間・1ヶ月・1年など一定の単位で労働時間を定める働き方のことです。
例えば、繁忙期に残業が多かったとしても、単位で定められた労働時間の合計を超過しない場合は時間外労働として扱われません。
一方、シフト勤務は、勤務日・勤務時間が固定されておらず、1週間や1ヶ月など一定の期間ごとに勤務日程を確定します。シフト勤務と変形労働時間制は、併用されるケースもあります。
ここでは、シフト勤務の対象となる時間について解説します。
1週間単位のシフト勤務(変形労働時間制)
1週間単位のシフト勤務の場合は、1日の労働時間を10時間以下、なおかつ1週間の労働時間を40時間以下と定められています。
各出勤日の就業規則時間は、直前の週末までに決定して、従業員に通知しなければなりません。
1ヶ月単位のシフト勤務(変形労働時間制)
1週間単位でスケジュールを決めにくい職業の場合は、1ヶ月単位で労働時間を決めることが可能です。
1ヶ月単位のシフト勤務の場合、月によって日数が変わるため規定時間が変わることに注意する必要があります。
規定時間は、1ヶ月が何週間かを計算して、週の労働時間の40時間を掛けて割り出します。なお、30分未満の端数は切り捨てます。
月の労働時間は以下のようになります。
- 1.3.5.7.8.10.12月ー177時間
- 4.6.9.11月ー171時間
- 2月ー160時間(うるう年の場合はー166時間)
1週間の労働時間が40時間を超えてしまったとしても、1ヶ月の労働時間が労働基準法で定められている規定の時間内であれば労働基準法違反にはなりません。
1ヶ月ごとのシフト勤務の場合は、期間が始まる直前の労働日までに通知する必要があります。
1年単位のシフト勤務(変形労働体制)
1年単位での労働時間を設定することも可能です。
1年単位のシフト勤務の場合も、1ヶ月単位のシフト勤務同様に、週の労働時間40時間で計算します。
そのため1年の労働時間は2,085時間となります。
このシフト勤務の場合は、月ごとのカレンダーを初日の30日前までに労働者に通知する必要があります。
シフト勤務に関する労働基準法のルール
シフト勤務を導入する際は、労働基準法で定められたルールを遵守する必要があります。ここからは、シフト勤務に関する労働基準法のルールについて解説します。
法定労働時間を超える労働には36協定が必要
『労働基準法』第32条では、1日8時間・1週40時間の法定労働時間が定められており、これを超えて働かせることはできません。
▼労働基準法 第32条
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』
法定労働時間を超えて働かせる場合には、時間外労働協定(36協定)を締結して、所轄の労働基準監督署長に届出を行う必要があります。
また、36協定を締結して時間外労働ができる時間は、原則として月45時間・年360時間と定められており、臨時的な特別な事情がなければこれを超えることはできません。
臨時的な特別な事情があり、特別条項つきの36協定を締結していても、以下のような時間外労働の上限規制が設けられています。
▼時間外労働の上限規制
- 年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について2ヶ月平均・3ヶ月平均・4ヶ月平均・5ヶ月平均・6ヶ月平均のすべて1ヶ月当たり80時間以内
- 月45時間を超える時間外労働は年6ヶ月まで
出典:厚生労働省『労働時間・休日』『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』/e-Gov法令検索『労働基準法』
法定外労働には残業手当を支払う
『労働基準法』第32条・第35条では、労働時間と休日について以下のルールが定められています。
▼労働時間と休日のルール
- 労働時間の原則は1日8時間・1週間に40時間
- 毎週1日または4週間を通じて4日以上の休日を付与する
▼労働基準法 第35条
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』
これを超えて時間外労働や休日労働を行わせた場合には、残業手当の支払いが必要です。また、残業手当の割増率は、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上と定められています。
変形労働時間制の場合であっても、法定外労働に対しては残業代として支払う義務があります。
時間外労働の割増賃金の計算については、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:厚生労働省『労働時間・休日』『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』/e-Gov法令検索『労働基準法』
労働時間に応じて休憩を付与する
『労働基準法』第34条では、労働時間が6時間を超える場合に45分以上、8時間を超える場合に1時間以上の休憩を付与することが定められています。
▼労働基準法 第34条
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』
休憩は、予定していた所定労働時間ではなく、実際の労働時間に対して付与する必要があるため、シフト勤務で予期せぬ残業が発生した場合には注意が必要です。
例えば、所定労働時間が6時間で45分の休憩を取得させたあとに、残業が発生して8時間を超えることになった場合、追加で15分の休憩を付与する必要があります。
また、来客や電話対応などの手待ち時間は労働時間として扱われます。休憩中に対応させた場合には、そのあとの休憩時間を伸ばしたり、勤務中に分割して取得させたりといった対応が必要です。
なお、アルバイトの雇用で気をつけたいルールについては、こちらの記事で解説しています。併せてご確認ください。
出典:厚生労働省『労働時間・休日』/厚生労働省 山梨労働局『休憩?手待ち時間??』/e-Gov法令検索『労働基準法』
シフト制労働契約を締結する際の注意点
シフト制の労働契約を締結する際の注意点には、以下の3つが挙げられます。
- 労働条件を明示する
- シフトについて労使でルールを定める
- 就業規則を作成する
労働契約の締結にあたっては、契約期間や就業場所、賃金の決定方法などについて定めた労働条件を従業員に明示する義務があります。
特にシフト制では、労働時間・休日が変則的になるため、トラブルにつながるリスクがあります。
労働条件通知書には、原則的な始業・終業時刻や休日の決め方について明記するとともに、シフト作成・変更に関するルールを定めて、従業員の合意を得ておくことが大切です。
また、常時10人以上の従業員を使用する事業者は、始業・終業時刻や休日に関する事項を定めた就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出る必要があります。
出典:厚生労働省『「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項』
シフトを効率よく管理するなら“シフト管理システム”の活用が有効
シフト勤務では、労働時間や休日、残業手当などのさまざまなルールがあります。
紙面や Microsoft Excel (※)を用いて、管理者が一人ひとりのシフトを管理しようとすると、時間・労力を要するほか、人的ミスも発生しやすくなります。
シフト管理を効率的に行うには、シフト管理システムの活用が有効です。
シフト管理システムの『シフオプ』は、あらかじめ設定したモデルシフトを基にシフト作成を行えるほか、労働時間や人件費を自動で算出できます。
また、労務コンプライアンスをチェックする機能が備わっているため、法定外労働の見逃しを防ぐことにもつながります。
※Microsoft Excel は、マイクロソフト グループの企業の商標です。
まとめ
この記事では、シフト勤務について以下の内容を解説しました。
- シフト勤務と変形労働時間制の違い
- 労働基準法で定められたルール
- シフト制労働契約を締結する際の注意点
シフト勤務では、労働時間や休日が変則的になることから、労務管理が煩雑になりやすいといった問題があります。
労働基準法のルールを遵守した労務管理を行うには、労働時間・休日・休憩を適切に管理できるシフト管理システムの活用が有効です。
効率的かつ正確なシフト管理を目指すために、シフオプの活用を検討されてはいかがでしょうか。
人気のコラム
大変なアルバイトのシフト管理を簡単に解決するツール「シフオプ」が便利!







